モジュラーデザインの戦略的実践
2024/11/30
モジュラーデザイン研究会の第10回講演会が11月7日に開催されました。 今回はSCANIA社の事例が発表され、モジュラーデザインを活用して自社の製品をモジュール化しようと活動されておられる多くの方々にとって有益な示唆が得られたことと思います。そこで、あらためてモジュール化におけるSCANIA社の活動を振り返り、モジュール化の設計プロセスを考えてみたいと思います。 さらに、同じ11月7日に発表されたヤンマー社の製品戦略としての活動を紹介し、一つの新たなモジュール化の事例として検証してみたいと思います。
1.モジュール化の意味とモジュラーデザインの位置づけ
モジュール化について、「実践モジュラーデザイン」で日野氏はその活動を分類しています。(図1)大きく「設計のモジュール化」と「生産のモジュール化」に分かれており、SCANIA社の実践を「設計的アプローチ」としております。それ以外のモジュール化の説明については「実践モジュラーデザイン」を参照してください。「設計的アプローチ」とは顧客要求から始まるエンジニアリングチェーンの設計プロセスを通してモジュール化するという事です。そのためにはまず、設計のプロセスを明確に定義し、各プロセスで製品のアーキテクチャーをモジュラー型にするための活動を実践していくことになります。
「実践モジュラーデザイン」では設計プロセスを定義する手法として「製品モデル」をまず確立することをお勧めしております。「市場要求」⇒「製品仕様」⇒「製品システム構成」⇒「設計部品構成」と展開することで、市場や顧客の要求仕様をどのような方式・機構・構造に展開し、具体的な機能部品にするかを明らかにします。インテグラル型の製品では、これらの展開で各項目間の展開関係が錯綜していることが多くなります。モジュラー型製品は各項目間の展開関係が単純になります。
2.モジュール化のプロセス
モジュール化を進めるためには、まず設計プロセスの各項目を見直すことが必要です。SCANIA社は市場要求の分類に特に注力したようです。今回の説明では“Clustering Customer”の要素として大きく“Industry”、“Operation”、“Application”、“Focus Area”を設定し、その中にさらに分類項目を作成していました。このような項目に分類されるまでには多くの試行錯誤が必要だったことは想像に難くありません。まずは自社の顧客の顕在的な要求項目と潜在的な要求項目を整理することが出発点です。このような整理を進めながら、製品仕様と機能モジュールを少しずつ変化させながら現在の機能モジュール群を整備してきたと思います。(図2)モジユール化を目指して完成するまでに20年を要したというのも納得できます。
モジュール化設計プロセスは、要求仕様を満たす製品仕様を展開し、それを実現する機能モジュールを決めていくという流れになります。(図3)しかもそのプロセスは、何度も循環しながら完成度を高めていく作業になります。
一般的な設計プロセスは製品機能をサブ機能に展開し、サブ機能を実現する機能部品を選択するという、右側の流れになります。モジュール化設計プロセスは、市場要求を整理し、それを実現する製品仕様(機能)を見直し、その機能をいくつかの機能部品で実現できるようにする左側の流れになります。市場要求から機能部品までの関係が明確になっていることが重要になります。製品をモジュール化するには、これら双方の流れを繰り返しながらモジュールを決めていきます。この考え方の詳細については、次回のモジュラーデザインアカデミー(2025年2月)でご説明したいと思います
。
3.モジュール化を前提にすすめる製品戦略と開発事例
ヤンマーホールディングス株式会社は、次世代ヤンマーデザインの“ありたき姿”を視覚化した「YANMAR PRODUCT VISION(YPV)」を発表しました。YPVから生まれたデザイン要素と、これまでヤンマーが培ってきたデザイン要素を融合したプラットフォームを構築し、2035年の農業や建設、海洋作業を見据えた革新的な設計思想により、農機や建機、ボートなどの製品ほか、サービスなども含めたプロダクトに順次適用していく予定です。(図4)ヤンマーは新たな取り組みとして「本質デザイン」の考え方に基づき、YPVに含まれるデザイン要素をプラットフォーム化することで、部材・設計の共通化に加え、未来の作業を見据えた新たなインターフェイスによる直感的な操作性や居住性も向上させていきます。また、開発工数の効率化や、コスト削減にも寄与していくことを目指しています。
今回提案されたYPVとは、様式にとらわれず本来の機能的な価値・意味を重視する「本質デザイン」の思想に基づき、2035年を想定して各事業の“ありたき姿”を視覚化したビジョンで、人に寄り添いながらも過酷な現場で耐えうる機械を製造してきたヤンマーのデザインを「柔和剛健」という言葉で表現しています。
YPVのデザインを通して定義された新しいデザインやキャビンの構造、HMI(Human Machine Interface)などの要素をプラットフォーム化することで、効率的な製品づくりと顧客価値向上の両立を目指しています。
以下分野ごとの活動を紹介します。
「大地(Land)」領域でのYPV
プラットフォーム化の一例として、従来のキャビン構造を見直し、農業機械と建設機械との部品の共通化の実現をめざしています。コンセプト農機「YPV-L」(Land)は、運転席に大型モニターを設置し、他の自動運転農機などをコントロールする司令塔としての役割を持たせています。さらに、完全自動化に向けたキャビンレス仕様を想定して、作業場所や作業者のニーズに合わせたカスタマイズを可能としています。 キャビンやシャシーをプラットフォーム化することで、農業機械と建設機械・自動運転機との部品の共通化を目指しています。 タイヤトレッドの調整を可能とし、幅広い作業に対応できるよう設計されています。
「都市(City)」領域でのYPV
「YPV-C」(City)では、今後増えると考えられるリノベーションや屋内作業を見据えて建機の電動化を推進します。災害時にはいち早く現場への移動が必要となるため、クローラではなく走行に最適なホイール(タイヤ)を採用。電動化で課題となるバッテリーの持続性と給電は、自走式バッテリー車で必要なタイミングに自動給電することを可能としています。
YPVに見られる設計上の特徴はいくつか説明されています。
- ①これまでよりキャビンの位置を前方に移動させることで、長時間作業する際の居住性を
大幅に向上させている。各部のプラットフォーム化により開発費用や工数を効率化する。 - ②内燃機やBEV、水素などマルチパワートレインでの展開を想定。エンジンルームと
ラジエーター部分との間に空間を設けて、冷却効率を高めたレイアウトを採用している。 - ③作業員がいない場所での自動運転化も視野に入れて
パンクのないエアレスタイヤを採用している。 - ④運転席には直感的な操作が可能な大型モニターを設置し
他の自動運転農機を制御する司令塔の役割も担っている。 等があげられます。
YPVの狙いは、製品が対象とする市場の変化(作業性の向上や操作員のスキル、容易なメンテナンス)や技術の変化(電動化の推進、ICTの活用、GPSとの連携)を盛り込んだ新たな製品群をそのプラットフォームから設計し、共通機能をモジュール化する試みです。それによって、開発効率とコストの削減、さらには市場要求への素早い製品投入を可能にすることを可能にします。 これまでに蓄積された技術や情報を整理し、新たな市場の変化を見据えて戦略的に製品群を見直す活動は、モジュラーデザインの国内での貴重な挑戦と言えます。
参考
■モジュラーデザイン研究会メールマガジン
モジュラーデザイン研究会メールマガジンではコラム・セミナー情報などをご紹介して参ります。
また、ご登録いただくと講義・講演資料・お役立ち資料のダウンロードをご利用いただけます。
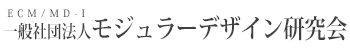
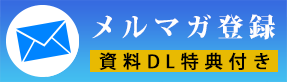
![図1:モジュール化の分類|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20241130-001.png)
![図2:スカニア社のモジュール化|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20241130-002.png)
![図3:モジュール化を進める設計プロセス|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20241130-003.png)
![図4:YANMAR PRODUCT VISION|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20241130-004.jpeg)
![キャビン設計の共通化と他事業展開|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20241130-005.jpg)
![自走式バッテリー車で電動建機に自動給電するイメージ|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20241130-006.jpg)



