ECMの体系を効率的に管理するツールPALMA®の活用事例
2024/12/31
2024年11月7日に品川でモジュラーデザイン研究会の第10回講演会が開催されました。当日はオンサイト及びオンライン同時開催として、約100名の方にご参加いただき誠にありがとうございました。本講演の中でも講演させていただいた「ECMの体系を効率的に管理するツールPALMA🄬の活用事例」について、ダイジェスト版として本コラムで振り返ってみたいと思います。
1.ECM/MD手法 システム化の課題
- ・2016年、故 日野三十四氏からもECM/MDを体系的に管理するシステムが世の中に無い
- ・ExcelベースのECM/MD手法では、データ連携も難しく、属人化されてブラックボックスになりがち
- ・2020年 PALMA®でECM/MDをOne Stopで管理できることを知り、調査を開始
2.ECM/MDを実現するための管理ツールの実態
- ・多くの企業はCRM、Doc管理、原価管理など各システムがサイロ化されており、情報が繋がらない
- ・PALMA®は要求管理から製品アーキテクチャ、モジュラー、製品の収益性までを効率的に管理
3.PALMA®でのECM/MD手法 実証
- ・ECM/MD手法のマーケティング情報DBや製品システム構成、製品企画手順における仕様の関係性を管理する機能を備えている
- ・ECM/MD手法の設計部品構成で管理された機能部品の製品ラインナップ表やモジュールテーブルを作成する機能を備えている
- ・PALMA®は属性と関係性をそれぞれ管理しているため、製品モデルの下流に属性を追加すると上流に情報が引き継がれる
4.システム化のメリットとPLM連携による設計自動化展望
- ・PALMA®の操作はシンプルで、ほぼ二元表で完結。製品モデルの上流からも下流からも作成できるため、ECM/MD手法に取り組みやすい
- ・PALMA®はPLMとの連携ソリューションも揃えているため、PALMA®でコンフィグした結果をPLMに連携し、BOMや3Dデータ構築も可能である(ECM/MD手法 設計文書編集システムに該当)
今回はECM/MD手法のシステム化が実現できるソリューションPALMA®を取り上げて実践しましたが、PALMA®以外にもECM/MD手法に近いシステムやソリューションが存在します。Excelフォーマットから脱却しシステムで管理することで、下流からも上流からもECM/MDを構築できるので、新製品開発だけでなく、既存製品へのECM/MDの適用ができる環境やシステムが整いつつあります。これまで、ECM/MDの重要さは理解しているが、どこから着手してよいか分からない方も多くいらっしゃると思いますが、PALMA🄬のようなツールを使うことでECM/MD手法を取り組みやすくなっております。
今後はPALMA🄬の上流工程で整理された製品構成や部品構成を出力し、PLMと連携してBOMやCADモデルの自動作成といったECM/MD手法 第6章 設計文書編集システムの検証を行ってまいります。故 日野先生が「どんなに良い設計手順書を作ってもそれが自動化されなければ設計者は使わない。使われないとすぐに陳腐化する」と力強く仰っていました。ECM/MD手法の実践に関する情報発信を引き続き実施していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
注:PALMA・ソフトウェアはModular Management社の登録商標となります
■モジュラーデザイン研究会メールマガジン
モジュラーデザイン研究会メールマガジンではコラム・セミナー情報などをご紹介して参ります。
また、ご登録いただくと講義・講演資料・お役立ち資料のダウンロードをご利用いただけます。
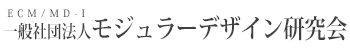
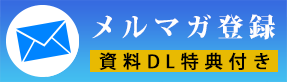
![図1:ECM/MD手法 システム化の課題|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20241231-001.png)
![図2:ECM/MDを実現するための管理ツールの実態|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20241231-002.png)
![図3:PALMA®でのECM/MD手法 実証|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20241231-003.png)
![図4:システム化のメリットとPLM連携による設計自動化展望|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20241231-004.png)



