モジュラーデザインを始める前にやっておくべき3つのこと
2025/3/31
―段取り八分で決まるモジュラーデザイン―
モジュラーデザインは新製品開発や新型機開発の時もまたは工場新設や刷新の時に適用すると効果が大きいと言われています。現行製品や旧型製品の部品種類削減は、すでに投資が済んでいるので制約条件が多く、成果が出たとしても活動効果は低くなります。
当面、新製品開発や新型機開発の予定工場新設・刷新の予定がなかったとしても、それらの開発を想定して進め、モジュラーデザインの効果・成果が予測できたら、タイミングをみて実際に開発に取り掛かることが必要です。いざ、進めようとしても一筋縄でいきません。そのためには、事前準備を進めておくことが重要です。
今回のコラムでは、モジュラーデザインの活動を始める前に、やっておくべき3つのことについて考えていきたいと思います。
1.モジュラーデザインを始める前にやっておくべき3つのこと
モジュラーデザインは、ベースモデルを基にした考え方で、流用設計とは別物です。目的である部品の種類(図面の枚数)を減らすには、顧客要求にさかのぼった標準化・モジュール化が不可欠となります。したがって、モジュラーデザインに取り組む前に、段取りを整え下記の準備活動をやっておく必要があります。
「モジュラーデザインを始める前にやっておくべき3つのこと」とは
- その1 目標・実行計画の立案:MDの活動の目標を設定して実行計画を立てる
- その2 製品モデルの確立 :製品知識と設計知識の集合体を確立する
- その3 モジュール数の理解 :モジュール数およびその使い方を確立する
2.その1 目標・実行計画の立案:MD可能性分析
(1) MD可能性分析簡易版の目的
図2は、MD可能性分析の簡易版のステップとアウトプットを表しています。MD可能性分析は、擦り合わせ設計された現状より、モジュラーデザインのあるべき姿へ向けての効果を、定量的に事前に予想することを目的としています。
MD可能性分析は、2~3週間で行う“簡易版”と2~3ヶ月で行う“詳細版”から構成されています。今回は簡易版について紹介させていただきます。簡易版の目的は、MDの活動を行うにあたり、対象の製品群に対しラインアップと構成部品のあるべき姿を検証し、事前に効果の可能性を定性的・定量的に把握し目標値を設定し、実行計画を組むことです。
- ・“製品仕様分析”により、現状の製品仕様・年間生産数・モジュール数を基準に最適ラインアップを検証する。
- ・“部品機能分析”により、固定変動分析・機能部品特性・メイン仕様との連動性より部品種類数の最適化を検証する。
- ・最適ラインアップと部品種類数の結果より、各部署のアクティビティー(活動)の効果をコストドライバーと連動させ検証する。
- ・現状の部門別固定費に対し、可能性分析結果より各部門の効果を推定し、目標値を設定し実行計画を組む。
(2) MD可能性分析簡易版のステップ
“製品仕様分析”と“部品機能分析”各分析のステップは、それぞれ5つのステップで構成されています。
■ 製品仕様分析:目標ラインアップ数の決定
Step1 出荷実績0製品削除
PQ(Product Quantity)分析の結果において、C分類の生産数0の品番に対して、調査・分析を行い、モジュール化対象品番か非対象品番かの区分を行う。
Step2 製品仕様の類似性分析
現状の製品体系から、MDを進める優先順序を決定するために、機能・構造の類似性の高い製品群を集めるために、製品の類似性分析を行う。
Step3 MD対象優先順序の決定
開発設計部門と生産技術・製造部門の管理指標のMD(Modular Design)指数とPMD(Product Modular Design)指数より、MDの優先順序を決定する。
Step4 最適分割数の検証
現状のラインアップを、基本性能をモジュール数、生産数大の仕様、コスト的に有利なラインアップより最適分割数を検証する。
Step5 ラインアップ低減余地の確認
最適分割数から求められた最適ラインアップより、現状との比較を行い固定費に対する低減余地率を確認する。
■ 部品機能分析:目標部品種類数の決定
Step1 現状のユニット・部品構成の明確化ユニットごとに部品展開し、現シリーズの総部品種類数、総部品数より全体の製品構成を把握する。 Step2 部品構成の固定変動分析
部品の固定変動分析にて、部品名と品番の関係を整理し、固定部品と変動部品の種類数を把握する。 Step3 品名レベルの機能部品特性分類
品名および構成部品に対し、“基本機能部品”“補助機能部品”“無機能部品”の機能特性の3種類に分類し、製品本来の目的に関与している部品の選定をする。
Step4 品名レベルの仕様連動性分析
各品名の種類発生要因に対し、“メイン仕様と連動”“サブ仕様と連動”“仕様と無関係に分類”の3種類に分類し、部品とメイン仕様との関係の重みづけをする。
Step5 目標種類数より削減効果の確認
「機能特性-仕様連動性」マトリックスより目標種類係数を選定し、各部品の目標種類数を設定する。
■ MD可能性金額の決定
製品仕様分析と部品機能分析の結果より、ラインアップ数削減率と部品種類数削減率を求め、将来の顧客ニーズを鑑み“+α”のラインアップは加味し、トータル的な削減率を推定します。 現状の各部門の固定費を経理部門より入手し、各部門の仕事の目的より得られる“コストドライバー”と上記の結果を踏まえ、各部門の部門別固定費の合計金額に”機種の低減率比率”を乗じ、MD可能性金額を決定していきます。■成果・効果管理指標の作成
部品種類数削減により各部門のアクティビティーを行うためのコストドライバーの効果より効果を、直接的な活動項目を管理する“成果管理指標”と具体的効果金額や物量値などの“効果管理指標”をアウトプットします。
“成果管理指標”は、金額以外の管理指標を向こう3~5年の計画を立てます。指標は、MD指数・PMD指数・モデル数・部品種類数・生産数/年・新規発生部品数などを設定していきます。
“効果管理指標”は、コストドライバーをベースに各部門の効果を、金額や比率、人数などで向こう3~5年の計画を立てていきます。
製品モデルは、What(何をつくるのか)を規定した「商品仕様構成」と、How(どのようにしてつくるのか)を規定した「製品技術構成」に大別され、構成は以下のようになっています。
(1) 商品仕様構成
客先からの機能要求と付帯条件を示した「客先製品仕様構成」と、それを社内での技術的な仕様表現に変換した「社内製品仕様構成」から成ります。
・客先仕様構成 : 客先からの機能要求と付帯条件を示したもの
・社内仕様構成 : 客先仕様を社内の技術的な仕様要件に変換したもの
(2) 製品技術構成
製品の機能を網羅した「製品機能構成」、機能を実現するための“仕掛け(方式、方法)”を網羅した「製品システム構成」、製品システムを物理的に実現する「設計部品構成」、および設計部品を生産する単位にくくり直した「生産部品構成」から成ります。それぞれの構成には、モジュール化された仕様項目と仕様値を登録します。
・製品機能構成 :製品の機能を網羅したもの
・製品システム構成:機能を実現するための仕掛け(方式・方法)を網羅したもの
・設計部品構成 :製品・システムを物理的に実現するもの
・生産部品構成 :設計部品を生産する単位にくくり直したもの
(3) 製品モデルの展開
商品仕様構成が決定したあとは、以下のステップで「製品システム構成」から「設計部品構成⇒生産部品構成」を展開していきます。
Step1 製品システム構成
製品機能を実現する方式、機構、構造などのシステムを展開した構成の作成
Step2 製品ラインアップ表
製品システム構成にモジュール数をベースとした、製品サイズを決定する要素を組み合わせた表を作成
Step3 機能系統図⇔方式・構造
機能系統図を作成し、機能とユニットに対する方式・構造との関係を明確にする
Step4 標準機能ブロック図
製品システムがどのような機能の流れになっているのかを明らかにすることを目的として、エネルギ、物質、信号を変換する機能を箱で示した機能の流れ図の作成
Step5 製品システム機能関係表
個別の製品システムを特定し、標準機能ブロック図にて不要な機能とそれにつながる線図を消去して個別製品システム用の機能ブロック図を自動作図するシステム関係表の作成
Step6 標準レイアウト図
複数の製品システムまたは部品をパラメトリック機能用の標準図として用いるため、最小公倍数的に包含したレイアウト図を作成
Step7 製品システム設計部品関係表
設計標準や個別製品の設計情報などの設計文書を部品の機能で一元的に管理することを目的とし、製品を構成する方式違いも含めたすべての部品を機能的に下方展開した構成の作成
Step8 設計部品構成⇒生産部品構成
設計部門では設計部品構成表にて、製品を構造別にユニット・部品へ機能展開を行う。一方、製造部門では機能展開された機能部品から生産部品への変換を行い、部品から製品へ加工・組立を行っていく工程をベースに、生産部品構成表を作成
4.その3 モジュール数の理解
(1) モジュール数(標準数)とは何か
モジュール数とは、図に示すように、ISO/IEC/JIS に登録された3 種類の数値表を総称していいます。3つのモジュール数は、設計パラメータ、部品諸元および電気値の製品諸元へ適切に適用します。ISO/IEC/JIS の世界的な知識人が、該当する製品諸元に等比数列を適用すると「製品の品揃え効率(=顧客獲得数÷品揃え数)」が最大化し、等差数列を適用すると部品と部品の互換性が高まると認定した規格です。
(2) 各モジュール数の概要
■JIS Z 8601 標準数 変化形態:等比数列
標準数とは図7に示す数値であって,10 の正または負の整数ベキを含み,公比がそれぞれ5√10 ,10√10 ,20√10 ,40√10 ,および80√10である等比数列の各項の値を実用上便利な数値に整理したものです。これらの数列をそれぞれR5, R10, R20, R40, R80の記号で表わします。
モジュール数は10のn乗を掛けて使います。また、必要に応じて1/10、100、・・・、10倍、100倍・・・してもよいです。したがって、等比数列の最終行は最初の行に戻って10倍すればよいため、最終行以下の数値の表記は省略します。
標準数の中で、実務的に良く使われる「誘導数列」と「変位数列」があるので、解説しましょう。
<誘導数列(間引き数列)>
ある数列のある数値から 2 つ目, 3 つ目,……, p 個日ごとにとって用います。この場合の数列を誘導数列という。なお, 2, 3, … , p をピッチ数といいます。製品仕様を決定する際、値の粗いR5より適用していくことがポイントですが、なかなか現実の仕様値に近い適当なモジュール数が見つけにくいのが現状です。そのようなとき、数値の細かい、たとえばR40の数値を当てはめ、図8のようにR40/4を実際の仕様値に近い数値を得られることがよくあります。
<変位数列(誘導数列の亜流)>
変位数列として用いるある数列によってきめられた特性に関係ある他の特性の数値を,同じ数列から採ることができないときに,この特性に適した数値を含む他の数列を選び,これを元の特性に等しい増加率をもつ誘導数列にしたものを用います。この場合の数列を 変位数列といいます。これは、仕様値のある部分では、顧客ニーズが細かいところと粗いところがある場合に使用します。
■JIS A 0001 建築モジュール数 変化形態:等差数列
等差数列数は公差が一定なので、設計の諸元値に適用すると、加算性と互換性が取れるようになります。加算性とは、等差数列数の中のどれかの数値とどれかの数値を足すと、どれかの数値に一致するということです。互換性とは、どれかの数値とどれかの数値を足した数値は、どれかの数値とどれかの数値を足した数値に一致するということです。
■JIS C 5063 抵抗器及びコンデンサの標準数列 変化形態:等比数列
抵抗器やコンデンサなどの受動素子の値についても、誤差(公差、許容差)を考慮した等比数列による数列表がJIS C 5063で規格化されており、こちらはE系列と呼ばれます。もともとは、素子の生産技術が未熟であった時代に、素子の特性値からの誤差を一定範囲まで許容することで不良品発生率を下げる、という考え方から生まれたもので、E3からE192まであります。
5.最後に
以上が、「モジュラーデザインを始める前にやっておくべき3つのこと」になります。
モジュラーデザインは製品開発プロセスを抜本的に改革する活動のため、一般の製品で約3年の月日を要します。したがって、活動をうまく進めていくためには“段取り八分で決まるモジュラーデザイン”を忘れてはなりません。
モジュラーデザインのコンサルティングの場では、
・受注はたくさんあるけど設計でこなし切れない
・特注の案件が設計工数を圧迫している
・個別受注対応で製品の品質が安定しない
・部品の種類が多く、設備投資金額が膨大になっている
・同じような機能なのに構造が違い、段取り替えが多く現場作業が非効率になっている
・金型治工具の種類が多く、管理工数と生産性に悪影響を与えている
・製品不具合の修理において、分解・組立が複雑で手間がかかる
・・・・
などの課題があります。
モジュラーデザイン活動の総論賛成・各論反対の呪縛から逃れるには、各部門の問題点を明確にして、開発設計段階で何をすべきかを関連付けて進めていくことが重要です。
現在、一般社団法人モジュラーデザイン研究会では、年に3回の“モジュラーデザインアカデミー”を開催しています。次回の開催は、6月17日(火)・18日(水)で会場は品川を予定しています。今回は、「DXイネーブラーとしてのMDを実践する」を1日、今回のコラムの具体的な解説の「モジュラーデザインを始める前にやっておくべき3つのこと」を1日予定しています。また、各社の事例も含め、モジュラーデザインの具体的な進め方を説明いたします。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。
【モジュラーデザイン・アカデミー講座概要】
■参考
■モジュラーデザイン研究会メールマガジン
モジュラーデザイン研究会メールマガジンではコラム・セミナー情報などをご紹介して参ります。
また、ご登録いただくと講義・講演資料・お役立ち資料のダウンロードをご利用いただけます。
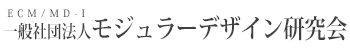
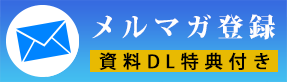
![図1 モジュラーデザインを始める前にやっておくべきこと|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250331-001.png)
![図2 MD可能性分析簡易版のステップとアウトプット|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250331-002.png)
![図3 ラインアップ低減余地の確認|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250331-003.png)
![図4 ラインアップ低減余地の確認|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250331-004.png)
![図5 製品モデルの全体像|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250331-005.png)
![図6 製品モデルの展開|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250331-006.png)
![図7 モジュール数(標準数)|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250331-007.png)
![図8:誘導数列・変位数列|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250331-008.png)
![モジュラーデザイン・アカデミー講座概要|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](../index_news/images/academy003.png)



