弊社の製品はモジュラー化されているはずなのですが
2025/8/31
― 標準化部品およびモジュラー化製品ユニットの管理に関する提言 ―
1.はじめに
日本における製造業のほとんどは30年以上の歴史を持ってグローバル市場において高い評価を受けておられます。この歴史の中で、コストダウンとリードタイム短縮は企業競争のテーマとして最上位に置かれて取り組まれておられるのではないでしょうか。ですので、筆者がコンタクトを取らせていただいているほとんどの企業ではコストダウンとリードタイム短縮を目的とした製品と部品の標準化やモジュラー化について、既に何らかの形で取り組んでおられるようです。特にマネジメント層やベテランエンジニアの方々からは「XX年前にモジュラープロジェクトをやったので当社の製品はある程度モジュラー化されているはずだ」というコメントをお聞きすることがあります。 一般社団法人モジュラーデザイン研究会が2025年7月に実施したモジュラーに関するアンケートに「貴社の製品のモジュール化推進状況を教えてください」という項目があり、この回答結果をみると、60%以上の回答が、何らかの形でモジュラープロジェクトを実施ている。もしくは実施した。と読み取ることができます。 しかしながら、実際にはクライアントの要望に応えるために、標準ラインアップに対して追加製品種類の増加、これに伴う部品種類数の増加、設計・調達・製造・在庫管理の複雑化が進行し、経営的にはコスト削減効果が相殺されているケースが多いのではないかと受け止められます。 これは、標準化・モジュラー化された構成要素に対する管理が不十分であることが原因の一つと考えられます。本コラムでは、標準部品およびモジュラー化ユニットに対して必要な管理項目を体系的に整理し、管理のタイプ別に分類・提案することを提案いたします。
■既に実施している標準化やモジュラー化の形
経験のある企業においては標準化やモジュラー化は既にある程度実施されておられます。ここに代表的なアウトプットの形態を紹介したいと思います。- 1 カタログに表わされた製品シリーズリストから売れ筋と在庫が多くなる製品を選別
- 2 製品の構成をストラクチャーで表現し、枝葉にバリエーションを持たせている
- 3 モジュールやユニットと呼ばれるサブアッセンブリーに対して担当する性能やキャラクターを持たせて表現
2. 管理の必要性と課題
前述のように「当社の製品は評価されている、モジュラー化されている」と言いながら複雑性が増している企業では、標準化、モジュラー化プロジェクトにおいて管理項目がしっかり定義されないまま俗人的なプロジェクトとなっていること、またプロジェクト活動終了後、一旦成果が上がったことでプロジェクトの成功をもって活動が終了しており継続的な評価と運営がなされていないことが原因と考えられます。この項目では、改めて企業における標準化・モジュラー化プロジェクトに対する現状評価と管理目的について周知することを提案いたします。2.1 現状の課題の認知
- • 標準製品およびこれを構成する標準部品の種類数が増加し、設計・調達・製造の複雑性が上昇
- • 標準化されたはずの部品が実際にはバリエーション化されている
- • 標準化やモジュラー化を行った際の背景情報が失われており結果の図面(データ)が残っている
- • 設計部門が担当して実施したため、直接原価低減要素だけに絞られている
- • 各部門での間接工数が可視化されておらず、経営的なコスト増加が見過ごされている
- • グローバル市場においてコストだけではなく循環経済社会への貢献として部品の再利用が新しい製品課題となる
2.2 管理の目的の周知
- • 標準部品の再利用率向上。モジュール、部品の再利用率の向上は所謂V字型開発プロセスにおいて単品(モジュール)機能要件とテストを繰り返し実施する必要性の排除につながる。(図1参照)
- • モジュールの設計・運用の一貫性確保。エンジニアリングチェインとサプライチェインの関係性を明らかにすることで、モジュール設計の持つ関係性と一貫性を確保することになる。
- • 間接工数の削減と経営指標への貢献。モジュラー設計は目的ではなく、経営目的を達成するための手段で有る認識。
2.3 全社組織横断で運営することの認識
- • 標準化・モジュラー化プロジェクトは経営目的を達成するために行うので、全社の誰がどのような関係性を持つのかについて事前に明らかにしてくべきである。
- • 経営目的としての売上・利益・顧客満足度向上などが標準化とモジュラー化でどのように達成されるはずである、という事前シミュレーションが行われるべき。
- • 上述のような目標達成について定期的な監視と評価と必要であれば軌道修正が行われるべき。
3. 管理項目の分類
ここでは、標準化やモジュラー化を実施する際に考慮されるべき管理項目について述べてみたいと思います。以下の管理項目のすべてを同時に実行するのはベストですが、企業や事業の置かれている環境に応じて順序や優劣をつけて管理を行うべきかと思います。また、モジュラー化で成功されている企業や事業の例を見ると、これらの管理項目を使って企業全体で取り組んでおられることが成功のキーのようです。3.1. 設計管理(Design Management)
管理項目:主に製品とユニット・部品の開発管理を行っている設計部門においては多くの管理項目に対して注力を行って標準化、モジュラー化に取り組む。- • モジュール定義の一貫性
- • インターフェース標準化
- • 設計ルールの明文化
- • 設計手順書の整備
管理目的:設計の属人性を排除し、再利用性と設計効率を高める。 - • モジュールの境界条件となるプロダクトプロパティ(製品特性)と、これを実現するための機能、性能、寸法、接続方式などを明確に定義。
- • CADテンプレートや設計ガイドラインを整備し、設計者間でのばらつきを抑制。
- • 設計変更管理(ECM)とモジュール構成の整合性を保つためのレビュー体制を構築。
- • 市場要求情報がいかに盛り込まれているか。
3.2. 調達管理(Procurement Management)
管理項目:従来設計部門などから出された部品手配依頼に基づいて調達を行っていた調達部門は部品の調達コスト削減の観点から、時には積極的に設計変更を依頼することがある。- • 標準部品の購買戦略
- • サプライヤー統合
- • 調達品目の共通化率モニタリング
管理目的:調達コストの最適化とサプライチェインの安定化。 - • モジュール単位でのサプライヤ契約(例:ユニット単位での一括調達)。
- • 標準部品の集中購買によるスケールメリットの活用。
- • 新品番発生の抑制。
- • 調達部品のバリエーションを定期的に棚卸しし、削減対象を特定。
3.3. 製造管理(Manufacturing Management)
管理項目:製造部門では製品と部品の複雑さに伴う工数が増えていることがある。サプライチェインの中のシチュエーションとして部品の保管と段取りについては部品種類数増加により作業が複雑化しており、保管に対するフットプリントも無視できないケースもある。- • モジュール単位の製造順序と組立設計
- • 工程の標準化
- • モジュール別の作業指示書
管理目的:製造の効率化と品質の安定化。 - • モジュール単位でのセル生産やライン設計。
- • 組立順序や治具の標準化による作業時間の短縮。
- • モジュールごとの作業指示書(SOP)を整備し、教育コストを削減。
3.4. 品質管理(Quality Management)
管理項目:品質管理部門においてはサプライヤからの部品受け入れに伴う品質管理やライン内での精度と品質に対する品質管理が行われているが、製品と部品の複雑性増加により作業プロセスも複雑化される。- • モジュール単位の検査基準
- • トレーサビリティ管理
- • 品質データのフィードバックループ
管理目的:不良率の低減と品質保証の強化。 - • モジュールごとに検査項目・基準を設定し、検査工程を簡素化。
- • モジュールIDやロット番号によるトレーサビリティを確保。
- • 品質不具合の発生時に、該当モジュール単位での原因分析と対策を実施。
3.5. 在庫管理(Inventory Management)
管理項目:在庫については従来の経営指標であるPLとBSではポジティブな指標となるためサプライチェイン担当責任者としては評価対象とならないこともあったようですが、近年は企業の多くがROIC経営を取り入れているため在庫を最小限にとどめることが目標となっています。- • 標準部品の在庫最適化
- • モジュール単位での在庫管理
- • ABC分析と安全在庫設定
- • 在庫が持つ経費の分析(フットプリント経費、運送ハンドリングコスト、金利、など)
管理目的:在庫コストの削減と供給安定性の確保。 - • モジュール単位での在庫配置(例:キッティング、ユニット在庫)。
- • 使用頻度に応じたABC分析に基づく在庫戦略。
- • モジュールの共通化率に応じた安全在庫の見直し。
3.6. IT管理項目(Information Management)
管理項目:標準化とモジュラー化に対して、これを「ITでどのように表現するか」についてはプロジェクトの成功を具体化することにおいて重要な管理項目です。- • 部品番号の統合
- • 意味あり品番による企業事業運営から、品名(モジュール名)+品番(モジュールバリアント)という形をどのようにITで表現するか。
残念ながらほとんどの日本の製造業は1970年代のコンピュータの制約から桁数に意味のある番号を使った部品番号がつかわれています。 - • PLM,CRM,ERPとの統合
管理目的:企業や事業における運営プロセスの整理と統合 - • 各アプリケーション間の接続
3.6. 経営管理(Management Control)
- 管理項目:
- • モジュール別の原価管理
- • 経済的効果の可視化(KPI)
- • 販管費との連動分析
-
管理目的:モジュール化の経営的効果を定量的に把握し、意思決定に活用。
- • モジュール単位での原価計算(設計・調達・製造・品質・在庫の各コスト)。
- • KPI(再利用率、共通化率、原価低減率など)の設定とモニタリング。
- • モジュール化による間接費削減効果と販管費の関係を分析。
4. 管理の実装に向けた提案
以上のように管理されるべき項目と目標については明らかになったと思います。これらを実際に適用して実装する方法についても簡単にまとめておきたいと思います。しかしながらこれらの実装については各企業の置かれているマーケットでの立ち位置、企業と事業の歴史や風土などによって実装方法が異なると考えられます。特に企業や事業が持っている課題をどのような順序で解決したいかによってさらに異なると考えられます。これが「モジュラープロジェクトはコピーできない」といわれる由縁ではないかと考えられます。- • モジュール管理台帳の導入:設計・調達・製造・品質・在庫の各部門が共通で参照できるモジュール情報を一元管理。
- • モジュール別KPIの設定:再利用率、原価、品質、納期などをモジュール単位で可視化。
- • モジュール責任者制度:各モジュールに対して責任者を設置し、横断的な管理を推進。
- • モジュラープロジェクト組織:モジュラー開発時には組織横断でリソースを集めて構築されるケースが多いのですが、一旦モジュラー化が終わると開催して各部門に戻ってしまうケースも多くみられます。システム開発の分野でもメンテナンス要員は開発要員と同じくらいのリソースを要すると言われているように、モジュール管理に対して組織化を行うことも大切なことです。自動車業界でMQB,MEBといったモジュラーアーキテクチャを開発し成功したと言われているフォルクスワーゲン社でも相当人数がモジュラー開発だけではなくメンテナンス管理とを行っているという報告があります。
また実装において過去の先人の教訓を取り入れることも重要なことではないかと思います。成功例は多くの事例として紹介されていますが、数少ない失敗教訓例はモジュラーで世界的に有名な企業であるSCANIA社が報告しています。これは、一旦開発されたモジュールが年月とともに顧客の要求を取り入れて、バリエーションを増やしていき複雑性によるコストが増えてしまったというものです。この図ではモジュラー化によって一旦は部品種類数が減ったが、新たな顧客要求を応えることで、次第に増える曲線に転じていった。これを再度減らす行為(ガバナンス)を行いStructured Governanceと書かれている部品種類数管理曲線へもっていった、ことを示しています。また、この教訓から同社ではモジュラー化を行う際に市場と顧客のニーズとシーズ、新技術の可能性など、過去と現在の情報だけでなく未来の情報に対してもモジュール部品に対する要求データとして扱うこととしています。
以下に、同社が行ったの顧客についての戦略的なとりまとめと、モジュラーの維持管理に行った施策についてまとめています。
1. 明確な戦略との整合性
モジュールは企業戦略と連動して設計されるべきであり、単なる技術的な構成ではなく、戦略的意図を反映する必要があります。長く使うモジュール、顧客のニーズに合わせるモジュール、アップデートで付加価値を向上させるモジュールが代表的な構成です。2. 標準化されたインターフェース
モジュール間の接続部(インターフェース)が標準化されていることで、設計の自由度と再利用性が確保されます。インターフェースの変更には各部門の影響が大きいため高いレベルでの承認が必要となっています。3. 機能の明確な定義
各モジュールが果たすべき機能が明確にすることで同じようなモジュールを開発をする必要が無いことを実践。例えば市内を走るデリバリートラックと市内を走るバスのサスペンションは目的と条件が同じであるため、同じでモジュールが使えるべき、問う考えです。4. 継続的なガバナンス体制
モジュールの追加・変更・廃止に関して、明確なルールと責任体制を実践しています。これにより、複雑性の再発を防ぎ、長期的な利益を維持できます。参考:モジュール管理ツールの実装例
スウェーデンに本社を持つModular Management社は、EricssonとErixonによって1999年に提唱された「技術的解決策をモジュールドライバーで評価し、MIM(Module Identification Matrix)でクラスタリング」という手法を使いモジュールそれぞれの特性を定義表現するというメソッドをシステム化してPALMAというアプリケーションとして提供しています。PALMAはQFDに代表される二元値表現でモジュールが持つ境界各種条件を定義しています。図2はPALMAが表現するモジュール管理の全貌です。
PALMAによるモジュール管理の主な機能と活用領域
PALMAは、製品アーキテクチャの構築・運用・改善を支援するSaaS型プラットフォームであり、モジュール化された製品群のライフサイクル全体を通じて、戦略的かつ実務的な管理を可能にします。1. 製品アーキテクチャの構築とモジュール定義
- • Module Builder:技術ソリューションのプロファイルに基づいて、製品をモジュールに分割する初期提案を自動生成。チームによる調整を経て最終的なアーキテクチャを確定
- • Module Strategy Matrix:各モジュールに対して「標準化」「安定化」「バリエーション化」などの戦略を設定し、企業戦略との整合性を確保
- • Interface Matrix:モジュール間のインターフェースを定義・管理し、設計者が誤ってインターフェースを破壊することを防止
2. 製品構成とバリエーション管理
- • GPS(Generic Product Structure):製品構造の汎用定義を行い、SKUや構成ルールを管理。ERPやCPQとの連携も可能
- • MVS(Module Variant Specification):モジュールごとのバリエーションを定義し、製品特性やパフォーマンスレベルに応じた構成を可能にする • Configuration Intent™:製品構成の意図を明示し、設計・製造・販売の各部門で一貫性のある運用を実現
3. 技術評価と意思決定支援
- • Design Property Matrix(DPM):製品特性を実現する技術ソリューションを評価し、標準化すべき要素とバリエーション化すべき要素を明確化
- • Concept Evaluation Matrix:複数の技術コンセプトを比較し、顧客価値の最大化に貢献する案を選定
- • Function Analysis:各技術ソリューションが果たす機能を分析し、重複や代替案を整理
4. 運用・実行支援
PALMAによるモジュール管理の導入効果
結論:モジュール管理の必要性とPALMAによる実装支援
これまでの考察では、標準化・モジュラー化された製品構成要素が管理されない場合、設計・調達・製造・在庫・品質・経営の各部門で複雑性が増し、結果として間接費や販管費が増加し、経常利益を圧迫するという実態が明らかになりました。 このような状況に対して、Modular Management社のPALMAは、モジュール管理を体系的かつ実務的に支援するプラットフォームとして、以下のような解決策を提供します。PALMA導入による期待効果
- • 設計・製造・販売の一貫性:製品アーキテクチャと構成ルールが統合され、部門間のギャップを解消。
- • SKUの最適化:バリエーション管理により、製品数を抑えつつ市場ニーズに対応。
- • コスト削減と利益率向上:再利用性の向上と間接費の削減により、経常利益の改善が期待される。
- • 戦略的意思決定の支援:製品戦略とモジュール構成の整合性を可視化し、経営層の判断材料を提供。
参照:
エンジニアリング・チェーン・マネージメント(ECM)をシステムズエンジニアリングで実践する(モジュラーデザイン研究会2024年5月31日コラム)
■モジュラーデザイン研究会メールマガジン
モジュラーデザイン研究会メールマガジンではコラム・セミナー情報などをご紹介して参ります。
また、ご登録いただくと講義・講演資料・お役立ち資料のダウンロードをご利用いただけます。
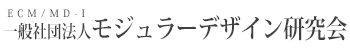
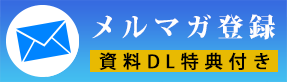
![図1:|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250831-001.png)
![図2:|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250831-002.png)
![図3:|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250831-003.png)
![図1: システムズエンジニアリングにおける製品開発プロセス|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250831-006.png)

![図1:|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250831-008.png)
![図2:PALMAが表現するモジュール管理の全貌|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250831-009.png)



