モジュラーデザイン実行手順簡易版_第六回:MDベースの設計・製造連携(全六回)
2025/7/31
本コラムの位置づけ
モジュラーデザインは非常に有用であり興味あるものの、実行手順が複雑で分かり難くそのため着手に踏み切れないという声を多く聞きます。そのため本コラムではモジュラーデザイン実行手順を簡易版として6回に分けてお伝えします。ポイントのみ分かりやすく可能な限り平易な言葉で表現しますが、あくまでもイメージの把握のためとなるので本コラムで紹介する簡易版だけでは実際の実行には情報不十分だとご理解下さい。まずはモジュラーデザインの全体感のイメージを把握していただき、より深く理解するきっかけとなることを目的としています。本コラムがモジュラーデザインの広い普及に貢献できれば幸いです。コラム構成(全六回配信予定)
- 第一回:第一章「モジュラーデザイン実行手順全体像」
- 第二回:第二章「製品モデル確立」
- 第三回:第三章「目標設定」
- 第四回:第四章「製品ミックス確立」
- 第五回:第五章「MDベースの設計・製造連携VE」
- 第六回:第六章「設計のモジュール化」
第六章「設計のモジュール化」
モジュラーデザイン実行手順の活動全体像を図1に示します。 設計のモジュール化の概要
今回の説明範囲である「設計のモジュール化」は活動項目の5番目にあたります。その主なアウトプットは以下となります。
- 設計手順書(設計フローチャート、モジュールテーブル、設計手順、設計解説書)
以降、設計手順書作成の実行方法についてそれぞれ紹介します。
「設計手順書」作成の目的と主なステップとポイントは以下となります。
目的- 設計の方法をインテグラル(擦り合わせ)型からモジュラー(組み合わせ)型に変える
- 設計者は図面を描かずに、事前設計されたモジュール部品のなかから選ぶ設計にする
概要
受注型・見込型生産ともに、OES(Order Entry System)と呼ばれる顧客が要望すると思われる仕様を事前に設計しておきます。設計内容は設計手順書として整理します。設計手順書とは設計へのインプットをもとに、次に何をするか、どのタイミングでどの設計根拠情報を参照するか、図面や部品表にどの設計からアウトプットするかを体系化したものです。手順書作成のなかで要求性能やレイアウトなどの設計パラメータのモジュール数値定義、部品仕様のモジュール数値定義も行います。
活動ステップ 機能VE
対象システム・対象部品の決定
- 1. 製品モデルの確立で作成した製品システム構成・設計部品構成から選ぶ
- 2. 基本的には、製品レベルから金型に直結する下位部品に向かって整備する
設計手順の整備
- 1. 設計インプット・事前収集情報・設計アクション・アウトプットを一覧化(カードに記載)
- 2. 一覧を時系列(インプット~アウトプット)に並べ、不足部分を追記し、フローチャート化
- 3. 各フローについて詳細の設計方法を記述
- 1. 設計手順の中に、仕様値・性能値・レイアウト値・寸法値・材料関連数値など数値に関するところをモジュール化する
- 2. 各仕様値の最小値と最大値を決め、その間に顧客要求と製造要求のバランスを取りながらモジュール数列を適用する
Point
部品の組み立て寸法値には等差数列を適用し、それ以外はほぼ等比数列を適用することになる
設計手順の文書化
- 1. 上記で整備した情報を、設計手順書として正式に文書化する
- 2. 手順書の様式は各社各様でよい。
今回は第六章として、設計のモジュール化のための、設計手順書作成方法について紹介しました。今回のコラムで全六章は終了です。過去のコラムもご確認いただけますと幸いです。また、このコラムで紹介したモジュラーデザイン実行手順書簡易版として整理したPPT資料もありますので、ご興味ありましたら当研究会までご連絡ください。
■モジュラーデザイン研究会メールマガジン
モジュラーデザイン研究会メールマガジンではコラム・セミナー情報などをご紹介して参ります。
また、ご登録いただくと講義・講演資料・お役立ち資料のダウンロードをご利用いただけます。
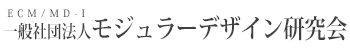
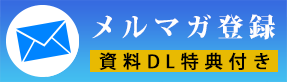
![図1:モジュラーデザイン実行手順の活動全体像|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20220430-001.png)
![図2:設計手順書の構造|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250731-002.jpg)
![図3:モジュールテーブルの例|エンジニアリングチェーンマネジメント/モジュラーデザイン研究会[ECM/MDI・PLM]](images/20250731-003.jpg)



